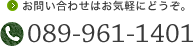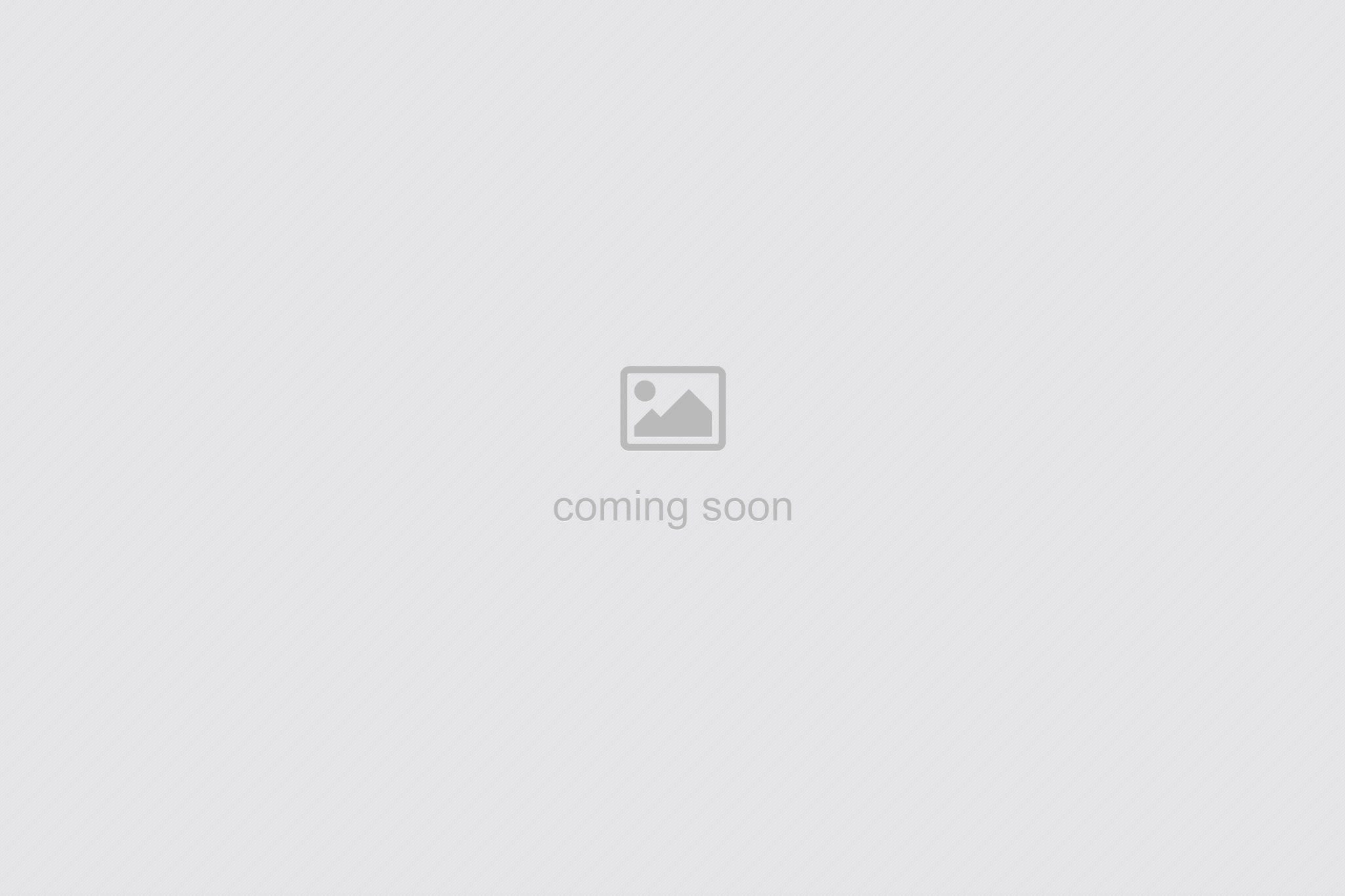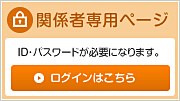ひーちゃんのつぶやき
付喪神とは
2018-03-07
「付喪神(つくもがみ)」というのを知っていますか?
「付喪神」とは長く使っている物や道具に神様が宿るという伝えがあり、付喪という字は「九十九」と書くそうである、「つくもがみ」という言葉は室町時代の御伽草子系の絵巻物「付喪神絵巻」に見られるものである。道具は100年経つと精霊を得てこれに変化することができるという。
「つくも」とは「100年に1年足らない」という絵巻の詞書きにあることから「九十九」(つくも)のことであるとされ、「伊勢物語」の和歌に見られる老女の白髪をあらわした言葉「九十九(つくも)髪」を受けて「長い時間(九十九年)」を示していると解釈されている。また九十九を「百」の字に一画足りない「白」になぞらえ、九十九髪を白髪と読み替え、転じて「長い年を経た」ことを指す言葉となった。
私たちが使っている物(パソコン・携帯・お皿・箸など)には「神様」が宿っていると考えら、まだ使えるのに古くなったから捨てようという人がいる、捨てられた物は「まだ使えるのに捨てられた」と思い妖怪になって仕返しをするのです。
今使っている物には「神様」が宿っていると私は思っている、友達がくれてコップやお皿・携帯ストラップなど大切に使っている、また父の形見も大切に使っている、これらの品物は私を守ってくれると信じてこれだけは捨てられない、もし捨てるとしたなら私に大きな罰が来そうでたまりません、日本では物をなるべく大切に使うようにするという精神が一般化し、古くなったものを使い続けることや、使い古したものも別の手法で再利用する文化が生まれました。それと同時に古くて使えなくなったものを処分する際は、お炊き上げ(人形供養や針供養など)と呼ばれる行事を行うようになり、物によっては大々的なイベントとして大勢で執り行うことも増えたといいます。
「もったいない」という言葉は残っておりリサイクルなどの考え方も学校や親の教育を通して伝えるよう努力していますが、「付喪神」の話が伝わることはほとんどありませんでしたがテレビゲームやアニメなどで付喪神のキャラクターが登場したりと、古くから伝わる付喪神の話とは違う形で付喪神の存在が若い世代に知られることのほうが多くなっています。
古くなってもすぐに捨てるのではなく、何かに使えるように考えるか、大切にしていた人形や服はまだ使えると思ったら友達にあげるかリサイクルに出すようにしてくださいね。
「つくも」とは「100年に1年足らない」という絵巻の詞書きにあることから「九十九」(つくも)のことであるとされ、「伊勢物語」の和歌に見られる老女の白髪をあらわした言葉「九十九(つくも)髪」を受けて「長い時間(九十九年)」を示していると解釈されている。また九十九を「百」の字に一画足りない「白」になぞらえ、九十九髪を白髪と読み替え、転じて「長い年を経た」ことを指す言葉となった。
私たちが使っている物(パソコン・携帯・お皿・箸など)には「神様」が宿っていると考えら、まだ使えるのに古くなったから捨てようという人がいる、捨てられた物は「まだ使えるのに捨てられた」と思い妖怪になって仕返しをするのです。
今使っている物には「神様」が宿っていると私は思っている、友達がくれてコップやお皿・携帯ストラップなど大切に使っている、また父の形見も大切に使っている、これらの品物は私を守ってくれると信じてこれだけは捨てられない、もし捨てるとしたなら私に大きな罰が来そうでたまりません、日本では物をなるべく大切に使うようにするという精神が一般化し、古くなったものを使い続けることや、使い古したものも別の手法で再利用する文化が生まれました。それと同時に古くて使えなくなったものを処分する際は、お炊き上げ(人形供養や針供養など)と呼ばれる行事を行うようになり、物によっては大々的なイベントとして大勢で執り行うことも増えたといいます。
「もったいない」という言葉は残っておりリサイクルなどの考え方も学校や親の教育を通して伝えるよう努力していますが、「付喪神」の話が伝わることはほとんどありませんでしたがテレビゲームやアニメなどで付喪神のキャラクターが登場したりと、古くから伝わる付喪神の話とは違う形で付喪神の存在が若い世代に知られることのほうが多くなっています。
古くなってもすぐに捨てるのではなく、何かに使えるように考えるか、大切にしていた人形や服はまだ使えると思ったら友達にあげるかリサイクルに出すようにしてくださいね。
長平良 洋史