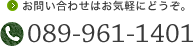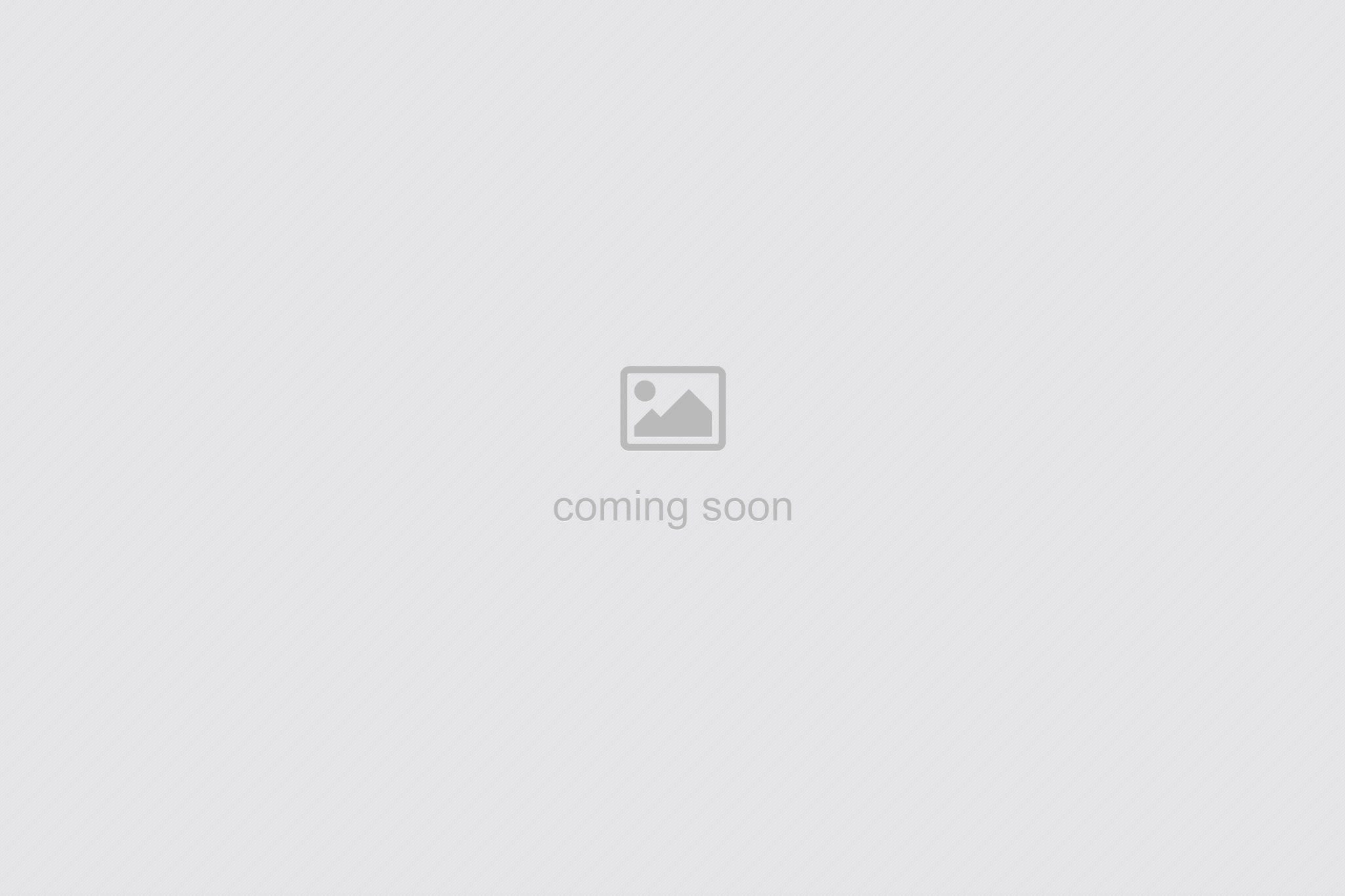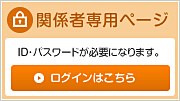ひーちゃんのつぶやき
飲みニケーションは必要?
2017-07-31
会社で花見やビアガーデン・忘・新年会をやるところもありますが、普段の仕事終わりに上司と部下がいっしょに飲みに行こうなんて少なくなりました
「飲みニケーション」とは普段会社にいてもあまり話さない社員に上司が距離を近づけるため、酒をくみかわしながらコミュニケーションを取る事である、これを奨励している企業や会社も存在しており、これを行うための手当を支給しているというところも存在する。
そんな楽しい場で部下に説教をしたり強制的に参加させたりする上司もいるそうだ。
昔、父も「一杯会」と称して若い教員たちと飲みに行っていましたよ、しかし父は「若い者の話にはついていけねぇよ」と言っていましたよ・・・
「一杯会」というのは打ち上げや飲み会の事で、打ち上げは全員参加で飲み会というのは行きたい人だけ行くというもので、飲み会でも若い教員たちの参加は少なかったという原因は校長や教頭がいるからというそれだけの理由、父は「一杯会は労を労う会だのになぜ参加しない、叱るわけでもないのに時代かな?」と嘆いていた。
若い人は若い人同士でワイワイとやりたいのではないかと感じた、そこに校長や教頭・父のような者が入ってくると言いたい事も言えない雰囲気なのだろう、その時から「校長や教頭・父のような学年主任」と「若手教師」の一杯会が行われるようになったと言っていましたよ、私は「それでいいのかな?もっと父のようないろんな先生の話を聴いてほしいな」って感じた・・・
「一杯会」というのは打ち上げや飲み会の事で、打ち上げは全員参加で飲み会というのは行きたい人だけ行くというもので、飲み会でも若い教員たちの参加は少なかったという原因は校長や教頭がいるからというそれだけの理由、父は「一杯会は労を労う会だのになぜ参加しない、叱るわけでもないのに時代かな?」と嘆いていた。
若い人は若い人同士でワイワイとやりたいのではないかと感じた、そこに校長や教頭・父のような者が入ってくると言いたい事も言えない雰囲気なのだろう、その時から「校長や教頭・父のような学年主任」と「若手教師」の一杯会が行われるようになったと言っていましたよ、私は「それでいいのかな?もっと父のようないろんな先生の話を聴いてほしいな」って感じた・・・
現代はビアガーデンや忘・新年会も参加しない人が増えてきたという、そういう現代に上司と部下が距離を近づけるためにやる「飲みニケーション」は必要なのか?
楽しいはずの「飲みニケーション」が説教をしたりアルコールハラスメントをしたり、ほかの嫌がらせをしたりする事がある、「飲みニケーション」自体悪い事ではないが無理やりに誘っても距離は縮まるどころか離れていくのではないのか?
会社や職場でコミュニケーションが図れない穴埋めを酒の場でしようとするのは本末転倒です。飲み会の席で本音を話せない職場なんてどんな職場なんだろうって思いませんか?
飲みに行けばお金もいる・家族を犠牲にしてまで行く時代ではない「飲みニケーション」は必要なのか?
昔は「飲むのも仕事」だと言っていた時代とは違うのです。
「飲む」といことは楽しみながらする事、説教とか嫌がらせをする場ではないのです。
酒の力でコミュニケーションを取ろうなんて考えが甘いのです、飲み会は年3回でいいが、その3回も仕事で行けない人もいるし家庭の事情で行けない人もいる。
「飲みニケーション」がしたいのであればまず働き方を変えるなどをする事でしょうか?
また、「社会」も変えないといけないのではないでしょうか?
長平良 洋史